欠片達の物語 プニートニフパニック 3
ヴァレンティナは、事故に巻き込まれた者達に手当たり次第に話を聞いていけばそのうち事件に関わる何かを知っている人物に辿り着くとは考えていなかった。その事は二年前に治安維持部が証明していたからだ。
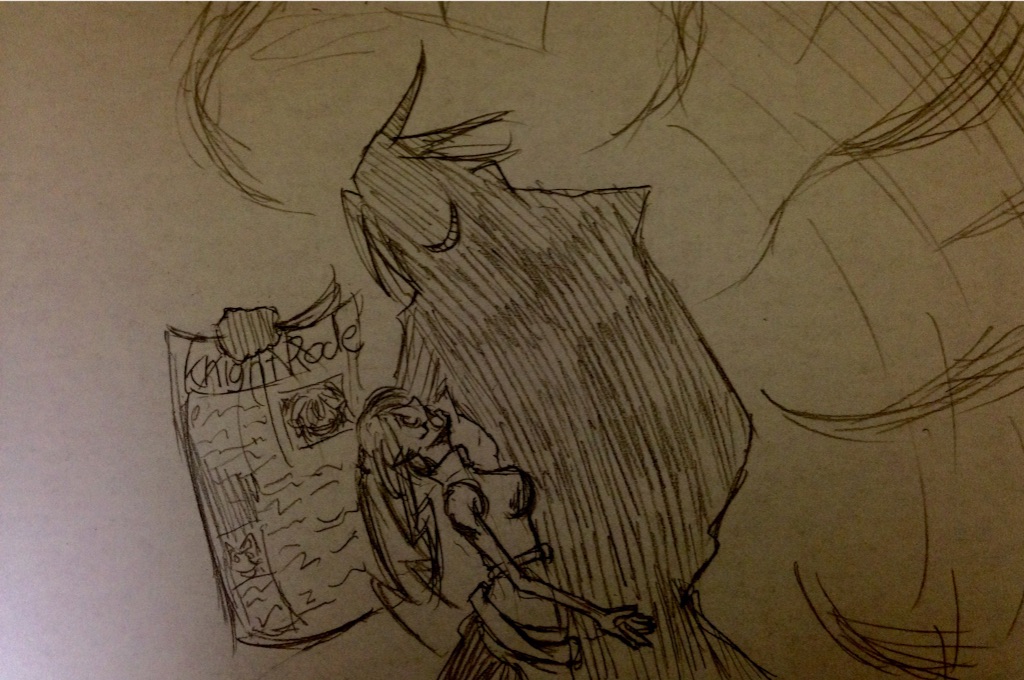
エクス・イグナイトは、ナイツロードにおいては特に重要な役職を持っているでもなく普通の一団員なのだがナイツロード内のあらゆる情報にことさら詳しく情報屋の一面を持っている男だ。その情報の中には時に幹部ですら知り得なかった事柄(団員の趣味嗜好や交友関係等)があったりするのだ。
ーまずはこの男に話を聞いてみようー
ヴァレンティナは、事件の被害者が治療を受けている医療室に足を向ける事にした。
ーPM 2:13 医療室ー
「やぁ、もしかしたら来るんじゃ無いかとは思っていたよヴァレンティナちゃん
プニートニフは元気かい?あいつの所為で右腕が暫く使えないようになってしまってね、今度あいつに俺が文句を言ってたって伝えてくれないか?」
「生憎てめえの右腕なんぞには一欠片の興味も無ぇし寧ろざまぁとすら思ってるから断る」
ニヤニヤしながらベッドに居座るエクスの周りには、お見舞いに渡されたのであろう沢山の花束が置かれていた。一緒に添えられているメッセージの字を見るに全て女から送られてきたものだろう。
「あいも変わらずモテモテのようだな」
ヴァレンティナが言葉を吐く。
「どういう訳か面会規制が入ってるもんだから可愛い彼女達の顔が見れないのが残念だけどねぇ」
ニヤニヤ顔を、ふとエクスは獰猛な笑みに変えながらこう続けた。
「・・・何か・・・・・吹き込まれたら困る事でもあるのかな・・・・・・?」
そう言って嫌らしい目をしたエクスは、包帯を巻かれた右腕を軽く振って見せた。
この場にはエクス以外にも多数の怪我人が寝泊まりしている。当然ナイツ・オブ・ラウンド「プニートニフ」の使役する魔獣によって傷を負ったものも少なくはなく、それどころかその傷が原因で死亡した者も多くはないが確かに居るのだった。
「・・・・・別に何かをチクられて困る事なんざぁ何もねぇよ」
「ふ〜〜〜〜〜・・・ん・・・・・?」
数秒間、重苦しい沈黙を場が支配した。ヴァレンティナはこの男と話すのが苦手である。この男と会話をする時はいつも、自分の心の中を無理矢理メスでこじ開けられて隅々まで覗き込まれている気分になる。エクスの周りにいつもいる囲いの気持ちが知れない。よくあんな怪しい男に心を許す気になるものだ。
「所で」
沈黙を破ったのは、目の前にいる女の顔を頬杖を突きながら面白気に見ていたエクスだった。
「用事があって来たんだろ?知りたいのは・・・今回の事件を起こした犯人かな?」
「あ、あぁ、情報屋であるてめえなら、何か知ってるかもしれねぇと思ってな
噂でもなんでもいい、どんな些細な情報でもいいから何か教えてくれねぇか」
「んー、300$でいいよ♪」
ヴァレンティナが札束をエクスの体に投げつける。
「毎度」
札束を確認する。
「確かに300$頂戴した
・・・それじゃ、特別に君にはこれを見せてあげるよ」
そしてエクスは左手を前にかざした、するとパソコンのディスプレイのようなものが浮かびだし、スーッと移動してヴァレンティナの顔の前で止まった。そこには、ナイツロードの基地内の図面に何かを囲うような丸、その横には日付が表示されていた。
「なんだこれは」
「なんて言ったらいいのかな、怪しい噂ってやつさ。その四月六日のはビビ・ルーニアが廊下を歩いていたら首筋の後ろから生温かい息を吹きかけられた所、五月三日のはフレディ・ボーニーが小さい影に襲われた所、その五日後の五月八日はアースラ・クワイエットが・・・」
「ちと待ちやがれ、それはあれか?コンビニの雑誌売り場に置いてあるちんけな怪談の本に書いてあるような内容じゃあ・・・」
「まぁ、団員の中では概ねそういった解釈で会話のネタに」
「てめえそんな事で300$払わせやがったのかこの」
「落ち着いて聞いてくれよミセス。いいかい?これが本当にそこらの町の雑誌コーナーに売られてるような本に書いてあるんなら鼻で笑われても仕方ないがこれは事実だ。本人に確認を取った時も嘘をついてるようには見えなかったしそれに、この狭い範囲でこんな連続して息を吹きかけられたり小さな影に襲われたり人が苦しむような声が耳元でずっと囁かれたり電気が点いたり消えたりするものか、なにより、被害者は口を揃えてこう言ってるんだ」
「なんだ」
「恐怖を感じたと」
「恐怖を?」
「そこはかとない恐怖を、足がすくむような恐怖を、息ができなくなる程の恐怖を、百戦錬磨の傭兵が、数々の死線を越えてきた兵士達がそんなちんけな怪談話に出てきそうなもので恐怖を感じたんだ。今回の事件のように」
「そのちんけな怪談のような話が、今回の事件に関係あるとでも?」
「調べてみる価値はあるんじゃないの?その日付のその場所の、監視カメラなり探知魔法器なり」
「・・・・・」
「ちんけな怪談だが・・・凄く『怪しい』ぞ」
「・・・分かった、調べてみよう」
そう言うと、ヴァレンティナは礼は言わずに踵を返し、その場を後にしようと思ったのだが・・・。
「今回の事件の事、外の連中は知ってんのか?」
「広報部の書いた騎士道団新聞?とかいうやつで大体の内容は伝えられてた筈だが」
「プニートニフが大量殺人者という事実は隠してか?」
「んだとエクス・・・ッ」
「ヒッヒッヒッヒッヒ。二年前と同じだなぁ、何もかもが、キャストが違うだけで同じ演劇を見ているようだ。」
「二年前とは違う。私が居る。この事件は解決する。」
「それはどうかな」
「それにだ。プニートニフを加害者みたいに言うのは止めろ、 あいつは『被害者』だ・・・ッ」
「それは無ぇ」
数秒間の沈黙の後、今度こそヴァレンティナは舌打ちをしてからその場を去るのだった。
医療室を出て少し進むとヴァレンティナはある小柄な少女に出会った。
「あ、ヴァレンティナさんこんにちは!」
「てめえは確か・・・・・フリーナ・・・だったか?」
「はいっフリーナ・ウォン・クリスタハートです。
・・・あのぉ、エクスにはまだ会えないんでしょうか?」
「悪いな、まだ療養中だ」
「うーん、会うくらいならいいと思うんですけど・・・」
「心に深い傷を負った人間ってのは何をやらかすか判らん、いきなり暴れたり襲ってきたりするかもしれないからな。まぁ、エクスは割と安定してはいるがそれでも念のため、な」
「ふーむなるほどぉ。じゃあじゃあそれならプニートニフさんは何処にいるんですか?」
「プ、プニートニフ?何か用でもあるのか?」
「はいっ!うち騎士道団新聞でプニートニフさんが獅子奮迅の働きでこの前の事件を鎮圧したって知って・・・」
「はぁ・・・」
「それでプニートニフさんにその武勇伝を聞いてみたいなーって」
「悪いなフリーナ、あいつもあいつでいつもふざけてる様に見えるが一応幹部でな、そう簡単にほいほいと一団員とは会えないっていうか・・・」
「そーなんですか・・・、それは残念です」
「あぁほんと悪いな、それじゃ」
「はい、お仕事頑張ってくださいねー!」
フリーナと別れたヴァレンティナは一人溜息をついた、内が読めない者と話すのも疲れるが純粋な少女を騙すのも心苦しいものだったからだ。
監視カメラや探知魔法器の調査を命じたヴァレンティナが次に会ったのはこれまた小柄な、しかし女性を象徴するそれは立派なとある魔族、そうプニートニフに会ったのだが、プニートニフはヴァレンティナには目もくれず横を通り抜けると。
「ちょっとなんなのさコレは!」
その先に居た中年の男ーーヴァレンティナのよく知っている人物ーーにこう問い詰めた。
「ん?いきなり何ですか、プニートニフさん」
「コレだよコレ!」
「これは・・・広報部出版騎士道団新聞、ナイツロード内で起こったあんな事件やこんな出来事をピックアップした・・・」
「そうじゃなくて内容の事!」
「毛色は白黒赤い首輪を・・・」
「なんでそんな迷子の子猫探しとかいうちっちゃな記事を真っ先に読んでんのサ⁉︎この一面のでっかい記事!」
「『再び起こった怪事件 解決したのはまたもやKORだった!』・・・あなたの輝かしい活躍の書かれた記事じゃないですか。何が不満なんです?誤字でもあったんですか?」
「誤字所か全てだよ!アタシは解決なんかしてない!むしろ暴走して沢山の人を傷つけてしまったと言うのになんでこんな事が書かれてるのサ⁉︎」
「えーー・・・、そんな事を聞きに来たんですか?」
「そ、そんな事って・・・⁉︎」
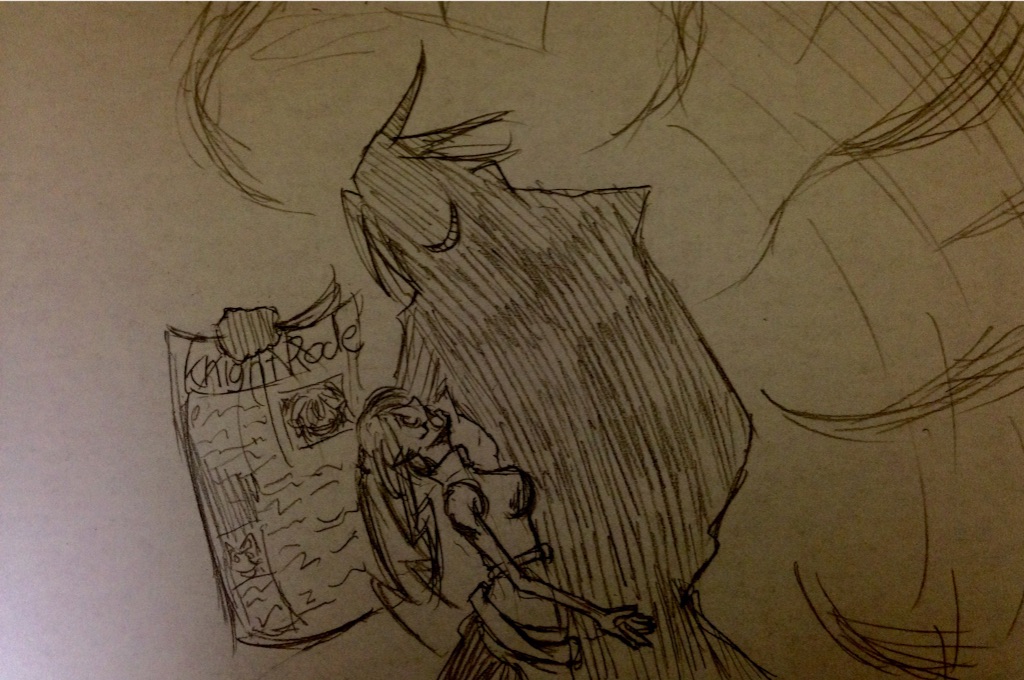
「ふーーーーーっ、いいですかぁプニートニフさん。貴女が暴れて多数の団員を殺害した。そんな事が知れたらKORの権威は失墜します。それを防ぐにはこうしないといけないんです」
「被害者は?今医療室にいる人たちが治って外に出たらそんな嘘直ぐにバレるんじゃないの?」
「安心しなさい。精神療法の一環としてこの事件の記憶は彼らの頭からは消去します。貴女のした事を言いふらす人間はいません」
「さ、最低・・・」
「最低?解りませんねぇ、記憶を消した所で誰が傷付くんです?被害者は嫌な記憶を消せてハッピー、貴女は今迄通りに暮らせてラッキーじゃないですか」
「だって・・・だって、そんな・・・・・」
「お話しは終わりですか?私も暇じゃないので・・・では」
そして男は三歩歩いた所で。
「あぁ、そうそう・・・プニートニフさん。しないとは思いますがぁ・・・この事を一般団員に言いふらしたらぁ・・・・・まぁ、言わなくても解ると思うんですけどねぇ?他の幹部の方にも迷惑がかかりますし・・・くれぐれも新聞のあの記事が嘘だなんて事、バラしちゃいけませんよ・・・?」
そう言い残して、その場を去ろうとした男だが、立っていた女ーーヴァレンティナの事であるーーに行く手を阻まれた。
「なんですかヴァレンティナさん、その顔」
「悪役の親玉かなにかかてめーは」
「おやそんなに悪そうな顔してましたか私」
「ああもうなんていうかいっそ清々しい位に悪(Vice)って感じだったぞ 少なくとも正義側の人間とは思えねー」
「結構、正義などという陳腐な言葉は夏の公園の公衆便所にでも流してしまいなさい」
「あんたの正義嫌いは相変わらずだな・・・。それよりも、プニートニフを必要以上に虐めないでくれ、あー見えてもまだ心の傷が完全に治った訳じゃない」
「それは失礼、責められてる女性てのはまぁ可愛いものでつい虐めたく・・・」
「死ねよ」
「直球ですねぇ!冗談に決まっているでしょう?」
「はぁ・・・、とにかくそっとしてやってくれ
・・・頼む」
「えぇ、えぇ、解りましたよ 長話が過ぎましたね、早く行かないと・・・あー、忙しい忙しい団長は忙しいですねぇ」
そういうと男は両手をポケットに入れてふらりふらりと歩き去って行った。彼こそは、ナイツロード団長「レッドリガ」その人であった。